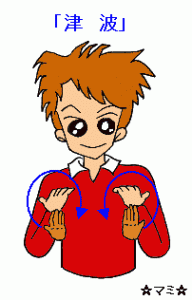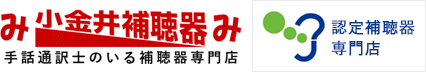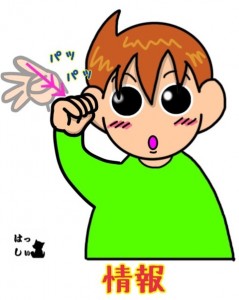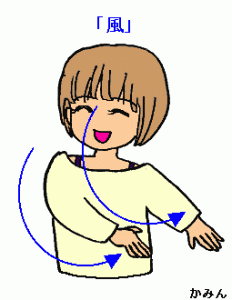気象庁緊急会見に手話通訳

気象庁は2019年3月25日、気象庁が行う緊急会見に手話通訳を付けると発表しました。
緊急会見は、震度5弱以上の地震や津波、火山の噴火、台風、大雨などが発生または予想された時に行われます。
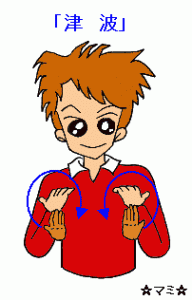
当面は9時~18時の日中の会見時のみになりますが、6月くらいからは24時間体制で行えるよう、動いているようです。
現在、首相や官房長官の会見に手話通訳が付いているのですが、登壇時にチラッとテレビに映るだけです。

後でYouTubeなどで見ることは出来ますが、生で手話通訳者が映っているのを見たことがありません。
台風通訳は、付かないよりは付いたほうが良いのですが、「ちゃんと付けてます」という言い訳か、パフォーマンスにしか思えない状況です。(もちろん、手話通訳者が悪いわけではありません。)
気象庁の緊急会見では、生で通訳者が映らないと意味がありませんので、必ずそうなるように期待しています。
UDトーク

耳のきこえに不便を感じている方々のために、最近はいろいろと便利なものが開発されていますので、UDトーク紹介させていただきます。
今回は『UDトーク』。
主に聴覚障害者と聴者のコミュニケーションをスマートホンやタブレット・パソコンを使用して行うためのソフトです。
2016年に施行された障害者差別解消法により、役所や病院等でよく目にするようになりました。発せられた音声が文字に変換されて表示されます。

しゃべるこが出来ない場合は、キーボードをたたいて文字を表わすことも出来ますし、キーボードが苦手な方は手書き文字で表すことも可能です。
視覚障害の方には、その文字を読み上げる機能もあります。
1対1の会話であればスマホやタブレットが1台あれば大丈夫ですが、数人の会議で聴覚障害者が何人か含まれるような場面では、一人1台ずつのタブレットを持って同じ画面を見ながら、あるいはそこに文字を打ち込みながら会議を進めます。
講演会のような場合、講師に専用マイクを持ってもらい、タブレットをプロジェクターに接続すると、文字通訳としてスクリーンに文字が表われ、聴覚障害者に講演内容を理解してもらうことが出来ます。

小学校で利用する場合には、何年生で利用するのかを設定しておけば、その学年に合わせた漢字やひらがなに変換されて表示されるということです。
役所や病院、企業、学校などで使用する場合は登録して利用料を払って使用しますが、個人では無料で利用出来ます。
ただ、誤変換防止の制度向上のため、無料で利用したデータは再利用されているようですので、重要なプライバシーに関する内容の場合は、無料での利用は控えたほうが良いと思います。
みえる電話

便利耳のきこえに不便を感じている方々のために、最近はいろいろと便利なものが開発されていますので、紹介させていただきます。
今回は「みえる電話」です。
NTTドコモが2019/3/1から始めたばかりのサ-ビス。
聞こえづらいので電話は苦手という方は多いと思いますが、Android6.0以上のスマホまたは電話機能付きタブレット、iOS11以上のiPhoneで使用することが出来ます。
使い方が大きく2つあります。
まず、聞こえづらいけどしゃべるのは出来るという方。
電話相手の声がスマホの画面に文字で表示され、
こちらは普通にしゃべるだけです。

次に聞こえづらくてしゃべるのも苦手という方。
相手の声はスマホ画面に文字で表示され、こちらの言いたいことも文字入力します。こちらが文字で伝えても、相手が聞こえる方の場合は、相手には音声に変換して伝えてくれます。
ドコモ契約のスマホでみえる電話アプリをダウンロードしてあれば、相手の電話はドコモでなくても、またスマホでなくても、家庭用電話でも会社の電話でもOKです。
送信時でも受信時でも、こちらがみえる電話を使用していることを、音声または文字で最初に自動的に相手に伝えます。

何か注文あるいは予約をしたい時や問い合わせをする場合、最近はインターネットやメールを使用することが増えてはいますが、電話でなければ受け付けてもらえないところが多いのも事実です。
急ぎの用件を電話で連絡しなければならない時などは、これを便利に使うことが出来ると思いますが、音声を文字に変換する場合、周りが騒がしかったり発音が明瞭でないと、正しく変換されないことがあるようですので、注意が必要です。
詳しくお知りになりたい方はこちらをクリック。
聴覚情報処理障害って?

最近、聴覚情報処理障害という言葉をよく聞いたり目にしたりするようになりました。
Auditory Processing Disorder:APDとも呼ばれています。
聴力検査をしても正常、つまりしっかり聞こえているのに言葉を聞き取ることが難しいという障害で、海外のある報告では、およそ7%の人がこれに該当するとしているものがあるようです。
特に次のような症状の特徴が…。
-
騒がしい場所では極端に聞き取れない
-
長い話を理解することが難しい
-
音声で伝えられたことは記憶しづらい
-
初めて聞く言葉は聞き取れないことが多い
-
聞こえたつもりの言葉を実は聞き間違えていた
原因としては頭部外傷、脳梗塞など、脳の器質的な障害がある場合が一部はあるが、器質的な問題はない場合が多いということです。
幼児期に長期間に渡り中耳炎の症状が続いたことや、睡眠障害なども原因として考えられるようですが、一番多いのが発達障害傾向だそうです。
また、発達障害には該当しなくとも注意力や記憶力など認知的な能力のアンバランは聞き取りに大きな影響を及ぼしているようです。
そして、その聞き取り難いという症状も、それを楽観的に考えられるか、それとも重く受け止め悩んでしまうのかによって、症状の進行具合や聞き取り難さの度合いが変わってくるそうです。
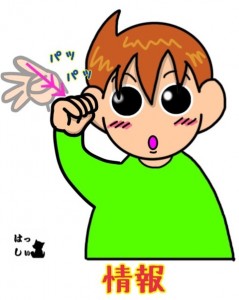
APDは改善させていくのが難しい場合もあるようですが、改善出来ることもあるようです。
まず聞き取る環境を整えることで、理解が大きく向上する場合があります。
一つは、周りを出来るだけ静かな環境にすること。
もう一つは、絵や図やジェチャーで示したり、難しい言葉は文字に書いて示すなど、目で見える情報も使って表すことです。
それから、数人以上の人が集まる場所で、皆が勝手にしゃべるような場合は使用出来ませんが、主な話し手が決まっている場合には、ワイヤレス補聴システムを利用すること。
リサウンドのマルチマイクやフォナックのロジャーのようなシステムです。
テレビやラジオをなんとなく聞くということではなく、しっかり聞くというトレ-ニングを行うことも重要です。
注意力や記憶力など、認知的な能力そのものを向上させ、耳で聞いて理解するという力が鍛えられます。
また、聞いて理解する力を高めるためには、聞く力を鍛えるだけではなく語彙数を増やすことも大切で、単語のある部分がハッキリ聞き取れなかったとしても、推測して聞き取れる幅が広がることになるようで、新聞や本を活用すると良いそうです。

理解そして、もしうまく聞き取れなかったとしても、聞き取れない自分が悪いと考えるのではなく、こんな環境では皆聞き取れていないはずと、自分を責めないようにすることが非常に重要になってくるということです。
耳のきこえがそれほど悪くないにもかかわらず、上手く聞き取れていないと思っている方はぜひ専門機関を受診されることをお勧めします。
補聴器と医療費控除

ネットの検索エンジンで「補聴器」と打ち込むとキーワード入力補助のトップに、“医療費控除”が出てきます。(多分、この時期だけの現象でしょうが)
以前は、補聴器を購入した場合でも、その費用は医療費控除の対象ではありませんでした。(一部、医療費控除の対象となる場合もありましたが)
それが2018年より制度が変わり、補聴器購入費も医療費控除の対象となりました。
ただし、どんな場合でも認められるわけではありません。

その話をする前に…。
補聴器を購入する場合、直接に補助金が出る制度が3つあります。
①障害者総合支援法の制度
障害者手帳(聴覚障害)を取得しているか聴覚系難病認定の方
②労災の制度税金
③軽・中等度難聴児に対する助成
①と②は国の制度ですので全国同じですが、③は各自治体が設けている制度ですので、
自治体によりその内容は異なります。
老人性難聴など①~③に当てはまらない方は、助成を受けることは出来ません。
ですが、確定申告をすることによりすでに払った税金の中から、補聴器費用の一部を戻してもらうことが出来る場合があります。
医療費控除を受けるには何が必要かというと…。
まず購入前、補聴器相談医の診断を受けなければなりません。
補聴器相談医は一番多い東京都で約400人、最も少ない県で20数人が登録されています。
そこで、補聴器適合に関する診療情報提供書を書いてもらいます。
その書類の中に、「補聴器を必要とする主な場面」という項目で、
□医師等による診察や治療を受けるために直接必要
という医師がチェックを入れる欄があります。
ここにチャックを入れてもらえない場合、補聴器購入費は医療費控除の対象になりません。
診療情報提供書は認定補聴器専門店か、認定補聴器技能者がいる補聴器販売店に提出しなければなりませんので、提出した際にコピーを取ってもらいましょう。
そのコピーしたものと、補聴器購入時の領収証の二つが、確定申告を行う際に必要となります。
どちらも提出する必要はありませんが、税務署から求められた場合には提示しなければなりません。

ちなみに①補聴器相談医、②認定補聴器専門店、③認定補聴器技能者がいる補聴器販売店はそれぞれインターネットで調べられます。
①は「補聴器相談医」で検索すると耳鼻咽喉科学会HPの補聴器相談医名簿のページが出てきますので、そこで見ることが出来ます。
また、テクノエイド協会HPの補聴器関係のページで②及び③を、補聴器技能者協会のHPで③を調べることが出来ます。
ゲートキーパー養成研修

先日、市が主催するゲートキーパー養成研修会に参加してきました。
行ってみてビックリ!参加者の多いこと。少し遅く来た当日申込の方は入れなかったのかもしれません。
ゲートキーパーとは「いのちの門番」
悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて必要な支援につなげ、見守る人のことです。
ゲートキーパーの方々が、年中無休で「いのちの電話」の対応をされています。
自殺の原因や動機として一番多いのは健康問題だそうで、そのなかでも一番多いのがうつ病の方。

その他の経済問題、生活問題、家庭問題、勤務問題などが原因となっている場合でも、最終的にはうつ的な精神状態に陥ると危険になってきます。
難聴が原因で他人との交流が少なくなり、うつの症状が出る方も少なくはないようですので、やはり難聴を放置しておくのはよくないと言えます。
また研修の中では“傾聴”に多くの時間を費やしました。
同じような講習を受けたことがありますしポイントは頭では分かっているつもりなのですが、本当に実践するのは簡単ではなく、仕事の現場でもそうすることが必要なのですが、出来てない時があるなあと反省しました。

最後に、ゲートキーパーを長年やっている方が質問に答えました。
ゲートキーパーをやるのに一番大切なことは?という質問に対して、まずは自身の健康管理だと。
自分が心身共に健康でないと務まることではないということ
身体が元気であるだけではなく、心も元気でないといけないというのは、私の仕事でも十分心しておかなければならないことだと思いました。
認知症と難聴・補聴器

最近、補聴器メーカーから届く販促品(冊子やポスター)に、認知症と難聴の関係に関するものが増えてきました。
これは、厚生労働省が策定した“新オレンジプラン”に大きくかかわっているものだと思います。
新オレンジプランの正式名称は『認知症施策推進総合戦略』といいます。認知症の方々へのサポートについてどのようにしていくのかということと共に、認知症予防をどう進めていくかということについて書かれています。

その中で認知症の危険因子として、加齢、遺伝性のもの、高血圧、糖尿病、喫煙、頭部外傷、以上のものと共に、難聴も挙げられています。
つまり、難聴をそのまま放置しておくと、認知症になる可能性が高くなるということです。
言葉による脳への刺激が減ることが認知症になる可能性を高める直接的原因になることと、聞きにくいことで社会的参加が減少することや、余暇活動の幅が狭まるというなどの間接的原因になるということです。
私も10数年前の補聴器販売時に2度同じようなことがありました。
軽い認知症により会話が時々かみ合わないことがあったりするお客様で、しっかりした聴力測定は行えない状況でしたが、ご家族の希望で補聴器を装用してもらうことになりました。

補聴器の着脱や紛失防止などご家族のサポートは大変だったでしょうが、2~3ヶ月でみるみる顔色や表情が明るくなり、新オレンジプラン①会話がズレてしまうことはほとんどなくなって、聴力測定もしっかり行えるようになりました。
補聴器で聞こえるようになったことが理由で、症状が改善したのかどうかは分かりません。
薬や治療の効果が出てきたのとたまたま時期が重なっただけなのかもしれません。

他にも同じような方に補聴器を使用してもらったことがありましたが、必ずしも上手くいったわけではなく、補聴器を着けてもいやがられたり、家族が見ていないところで外して失くしてしまうこともありました。
聞こえるようになることで、認知症が改善するとまでは言えませんが、聞こえるようになることで、認知症を発症する可能性が低くなることは知られています。
ろう者のバス運転士

松山建也さんは、現在日本でただ一人の“ろう”のバス運転士です。
2016年4月に運転免許制度が改正され、聴覚障害者でも補聴器を装用して、一定基準(10m離れて90dBのクラクション)の音を聞くことが出来れば、二種免許を取得することが出来るようになりました。

二種免許が取れれば、バスやタクシーの運転手として仕事に就くことが出来ます。
観光バスの運転士になるのが夢だった松山さんは、それまで大型免許を持ってトラック運転手として仕事をされていました。

運転免許制度改正によって大型二種免許を取得出来るようにはなりましたが、実際にバスの運転士になるのは簡単なことではなかったようです。
なにしろ、日本にはそれまで“ろう”の運転士は一人もいなかったのですから。
二種免許を取得したろう者はこれまで40人以上いるようですが、実際にその仕事に就いているのはまだ松山さんだけでしょうか。
その松山さんの講演会を、小金井手話サークル主催で2月23日の15~17時で行います。
参加費は無料です。多くの方の参加をお待ちしています。
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
自転車には外マイク補聴器!

小金井補聴器のお客様の中に自転車競技をされている方がいらっしゃいます。
自転車のロードレースは、100Km程度かあるいはそれ以上の長い区間を交通規制をかけて車をストップさせますので、陸上のマラソンのようにあちこちで頻繁に行われているわけではないようです。
そのお客様はプロの選手ではありませんが、国内のレースはもちろん海外のレースにも参加されています。
補聴器装用経験は短くはありませんが、これまでずっと耳かけ型補聴器を使用されていて、レースの時は風切り音が邪魔になりますので、補聴器は外して参加していたそうです。

自転車レースだけではなく、仲間とのツーリングでも、休憩中などは補聴器があったほうがよいのですが、荷物は出来るだけ少なくしますので、補聴器を持っていくことはあきらめていらっしゃいました。
私はテレビで自転車ロードレースを見たことはありましたが、詳しいことは知らず、話しを聞いて驚いたのですが…。
自転車のレースは個人競技であっても実際に走っている場合は、近くを走っている選手と協力し合って走るそうで、数人(場合によっては数十人)でチームのようになり、先頭を入れ替わりながら出来るだけ風の抵抗を受けなくて済むようにして集団で走るそうです。
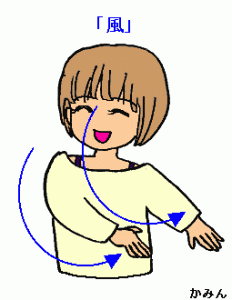
平昌オリンピックのスピードスケート女子で金メダルを取った、チームパシュートを思い出していただくと良いですね。
ただ、自転車では同じチームや仲間ではなく、例えばライバル同士であったとしても、ある一定の時間や距離の間では協力し合うようです。
そして、それまで少し離れて走っていたのに、近づいてきたので「しばらく一生に走ろう!」とか、しばらく一緒に走っていたのに、もう体力的についていけなくなった時、「もう自分はムリ、先に行ってくれ」とか、その逆で、集団のスピードが落ちてしまって「今までありがとう、先に行くね!」などという時に、基本的には手の動きなどで合図を送るのですが言葉をかけあうこともけっこうあるということ。
ただ、その方は、自転車に乗っている時に言葉でコミュニケーションを取ることはあきらめていらっしゃいました。
ところが、ホームページで補聴器を紹介しているコーナーで、“外マイク耳あな型は風切り音が気にならない”と私が書いていたのを見つけられて来店いただきました。
補聴器を作製して試聴していただきながらその間にマイクチューブの長さの変更など行い、自転車で走っている時でも話しができるということで、まだ十分使用出来る耳かけ型補聴器をお持ちであるにもかかわらず、外マイク耳あな型補聴器の購入を決めていただきました。
私も、補聴器を着けて扇風機の風をあびたり、風の強い時に外に出て使ったりして効果は体験していましたが、ここまで外マイクのメリットを感じていただいたお客様に、実際にお会いするのは初めてで、ホームページの補聴器紹介の箇所に、わざわざ外マイク補聴器の欄を作って良かったと改めて感じたところです。
補聴器の価格帯別構成比
昨年一年間で出荷された補聴器の価格帯別の割合が出てきました。
構成比は下のグラフのようになっています。
この価格はカタログに掲載されているメーカー希望小売価格になります。
店舗によっては多少値引きして販売されている場合もありますが、値引き前の価格ですので、実際の販売価格帯とは少し違ってきます。
また、両耳同時購入の場合、単純に片耳価格×2ではなく、割安なメーカー希望小売価格が設定されている場合もありますが、それも割引前の価格で計算されています。
充電タイプの補聴器では、充電器の金額は引いた価格になっており、また、器種によってはオープン価格で希望小売価格の掲載がない物もありますが、それはこのグラフには含まれていません。
10万円以下の中では、総合支援法対応器種とポケット型で約半分。
補聴器の出荷台数で耳かけ型は耳あな型のおよそ2倍の数になっていますが、どの価格帯でも耳あな型と耳かけ型の比率はおよそ1:2になっています。(10万円以下の価格帯を除く)
以前は、耳あな型は少し高価格になる傾向がありましたが、現在ではその傾向はほとんどなくなってきているようです。
※10万円以下の耳あな型は元々少ないので、その価格帯では耳かけ型の比率が大きくなっています。
小金井補聴器でも価格帯の比率はほとんど変わりません。平均で約20万円、高価な補聴器では50万円を超えます。
一生に1回だけ購入すればずっと使用出来るというのであれば良いのですが、数年で買い換えが必要になってくるのにこの価格です。
日本では補聴器の普及が進んでいないことはこれまでも言ってきました。2018年は2017年と比較して4%伸びていましたが、10年前と比較して27.1%。年平均にしてやっと2%を超える程度しか伸びていません。
販売台数が増えてくれば、当然価格は下がってくると思いますが…。
売れないから価格が下がらないのか、価格が下がらないから売れないのか、
悪循環が起きているのでしょうが、補聴器業界が力不足なのは明らかです。
販売数が伸びれば、価格は今の半額くらいになってもいいのではと思っています。
そんな時が早く来るよう、多くの方に補聴器を使ってみたいと思ってもらうために、
まだまだ考えなければならないことがいろいろとあるようです。